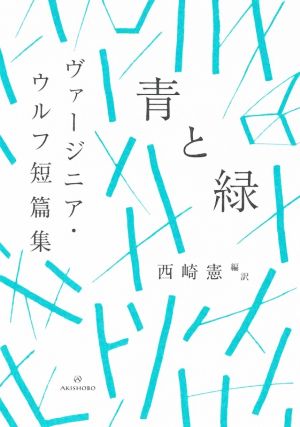
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
青と緑 ヴァージニア・ウルフ短篇集 ブックスならんですわる01
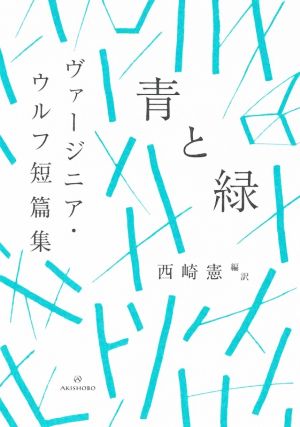
定価 ¥1,980
¥990 定価より990円(50%)おトク
獲得ポイント9P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
6/14(金)~6/19(水)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 亜紀書房 |
| 発売年月日 | 2022/01/19 |
| JAN | 9784750516929 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
6/14(金)~6/19(水)
- 書籍
- 書籍
青と緑 ヴァージニア・ウルフ短篇集
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
青と緑 ヴァージニア・ウルフ短篇集
¥990
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
4.5
4件のお客様レビュー
代表作「キュー植物園」など20篇を収録した短篇集。 以前から唱えている〈ヴァージニア・ウルフ=少女漫画説〉が、この短篇集を読んでより自分のなかで強固なものになった。小動物や植物、世間的には取るに足らないとされる小さなものたちにシンパシーを感じ、そこに個人的な象徴や啓示を見いだ...
代表作「キュー植物園」など20篇を収録した短篇集。 以前から唱えている〈ヴァージニア・ウルフ=少女漫画説〉が、この短篇集を読んでより自分のなかで強固なものになった。小動物や植物、世間的には取るに足らないとされる小さなものたちにシンパシーを感じ、そこに個人的な象徴や啓示を見いだしていくモチーフの使い方。ディテールに注ぐ偏執的な凝視。言葉になる前の不定形な感情をとらえようとしてあふれだす、言いさしのような未然の文体。 これらはみな、萩尾望都や大島弓子などの作品にある謎めいたほのめかしや、わかりきれないけど「わかる」と思わされてしまうモノローグの魅力にとても近いのではないか。漫画家が絵と言葉を組み合わせて表現するものをウルフは言葉だけで表したと思えば、目指していた場所はかなり接近しているという気がする。文章で「バナナブレッドのプディング」を書いたような人だということだ。 たとえば表題作「青と緑」は、マントルピースの上に飾ったものたちの世界を異様なクロースアップで幻想を交えながら描写する。「乳母ラグドンのカーテン」ではカーテンのなかに世界が広がり、「壁の染み」ではたったひとつの染みに対して数多の可能性が検討される。空想というより妄想と言うべきその世界は、家という静の空間で自らも静の存在となって対象を凝視している語り手の窒息感みたいなものが伝わってくると思うのだ。 最初に置かれた「ラピンとラピノヴァ」は新婚カップルの蜜月期を描いたユーモラスな作品だが、ラスト一文の切れ味といったらない。ロザリンドはアーネストと一緒に窒息感からの逃げ場所を作ったのに、それが崩壊してももはやアーネストはひとりで新聞を広げて読みだすだけ、という完全な断絶に、ロザリンドと同じく読者も絶望する。 男が新聞を読む描写は他作品にもくり返し現れる。女性がこまごまとしたインテリアを見つめて意識の〈内〉の世界へ飛んでいくとき、男性は新聞やホイッティカー年鑑を読んで〈外〉の世界へ飛んでいる。この断絶。だが、「堅固な対象」の主人公は男性でありながらも小さくてくだらないものの側につく。そのために彼は政治という世間的な価値のある世界からは離れていく。 前時代的な家観に息苦しさを感じながら動けずにいる人びとを書く一方、「外から見たある女子寮」は恋の予感に浮き足立つ少女の一夜を描いた瑞々しい作風で他と違う印象を残す。この作品はシチュエーションも含めてかなりストレートに少女漫画っぽい。女性同士の同性愛という、従来的な"家"からは逸脱する関係をほのめかしているということも重要だろう。 あるいは、他の誰かになりかわることが一種の解放をもたらすこともある。「サーチライト」では、偶然漏れ聞こえてきた声すら即興的に取り込んでしまうほど巧みな語り部が、サーチライトと望遠鏡の類似に幻惑されて自分が語る話のなかに入りかけてしまう。語っているのか語られているのか曖昧になり、演者自身が自分の台詞を信じ始めてしまうような演劇空間の神秘が、サーチライトに照らされた夜の庭に幻出したのだ。少し乱歩の「押し絵と旅する男」を連想させるところがある。 訳者解説によるとウルフの作風は「不安を惹起させる Unsetting」と評されているという。たしかに、一匹の蝸牛をねっとり見つめたかと思うと来園者の話に聞き耳をたて、最後には天高い視点から植物園を睥睨する「キュー植物園」の語り手は語りの対象との遠近感がめちゃくちゃで得体がしれないし、死者と生者が鏡合わせのように語られる「憑かれた家」も、不思議なあたたかさがありつつ落ち着かない気分にさせられる。土地の精霊[ゲニウス・ロキ]的な存在が人や生き物に自由に出入りして思考をのぞいているようだと言えばいいのか。読心ができたら世界はこんなふうなのかもしれない。 原題がそのままSympathyな「同情」という一篇からもわかるように、ウルフは知的でありながらも自他境界をたやすく踏み越えてしまうような女性もよく描く。共感力の高さによって浮遊霊のように人や動物やものたちに乗り移り、その意識に同調する。それが〈意識の流れ〉という方法でウルフが捉えようとしたものなのではないだろうか。そしてそういう魂を持った人が社会的にあるいはジェンダー的に自身の肉体に縛られている苦しみと虚しさ、それが私には昭和の少女漫画家が身を削って描きだした世界の在り様と完全に重なって見えるのである。
Posted by 
半分以上は「どういうこと?」という感想だが、私も普段思考があっちこっち行くのでそれを可視化できる意識の流れが書かれている話は面白かった。
Posted by 
今の自分には合わず、半分ほどで挫折。 でも「堅固な対象」がものすごく好きで、これだけでも手元に置きたいと思った。
Posted by 


