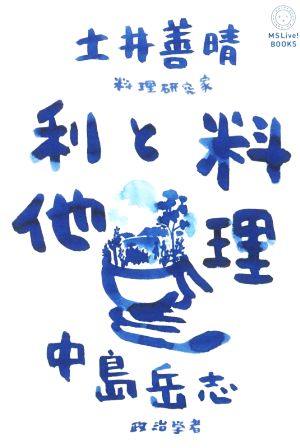
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
料理と利他 MSLive!Books
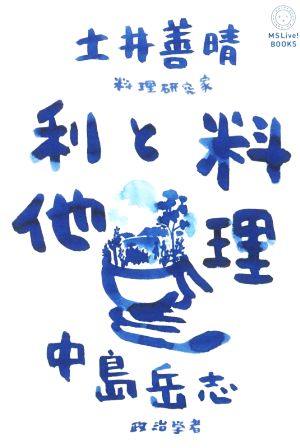
定価 ¥1,650
¥770 定価より880円(53%)おトク
獲得ポイント7P
在庫あり
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
6/4(火)~6/9(日)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | ミシマ社 |
| 発売年月日 | 2020/12/15 |
| JAN | 9784909394453 |
- 書籍
- 書籍
料理と利他
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
料理と利他
¥770
在庫あり
商品レビュー
4.1
36件のお客様レビュー
リモート対談の書籍化。 政治学者と料理研究家という異色の組み合わせながら、 日本の家庭料理から日本の社会のことが分かるという とても示唆に富む本だった。 あるものに足していく、計量など数字で示す西洋料理と、日本料理との違い。 ハレとケが両方存在するのが家庭料理で、 料亭のような栄...
リモート対談の書籍化。 政治学者と料理研究家という異色の組み合わせながら、 日本の家庭料理から日本の社会のことが分かるという とても示唆に富む本だった。 あるものに足していく、計量など数字で示す西洋料理と、日本料理との違い。 ハレとケが両方存在するのが家庭料理で、 料亭のような栄養価よりも見た目の美しさを取るハレの料理だけでなく、 疲れている時に簡単に済ませるようなケの料理もある。 日本料理は、素材のそのままと、作る・食べる人の身体の状態と、 かけられる時間を考えたら、おのずと方向が決まってくる、 というのが目からウロコだった。 決まった形にそって選ぶのではなく、全体を考えるとそうなる。落ち着く場所がある。 器ひとつからでも、見合う料理・盛り付け方は決まる。 家で作る料理の手を抜いても、おいしくなくても大丈夫、と プレッシャーから解放される読まれ方もあるだろうし、 ここから日本の文化、精神性、さらに世界の持続可能性をも知ることもできる。 こんな評論がもっと増えたら面白い。
Posted by 
期待通り、すごく面白い本だった。 印象に残った箇所。 p30 土井 日本がいちばんだなんて言うつもりはなにもないけれど、西洋や中国をはじめとして世界中が、磁器という近代の便利な清潔感のある道具を使っているなかで、日本では、土の陶器や漆器、ガラス器も一緒に使ってるわけでしょ。道具...
期待通り、すごく面白い本だった。 印象に残った箇所。 p30 土井 日本がいちばんだなんて言うつもりはなにもないけれど、西洋や中国をはじめとして世界中が、磁器という近代の便利な清潔感のある道具を使っているなかで、日本では、土の陶器や漆器、ガラス器も一緒に使ってるわけでしょ。道具の多様性は自然です。このへんが日本人らしさ、自然との距離感、そういうものを物語っていると思うんですね。 p52 土井 レシピを意識した途端に、人間という生き物は感覚所与(五感)を使わなくなるんです。なにかに依存すると感性は休んでしまうようです。 →や、これまさにそうだと思う。あまりにも「スマホで検索」に依存すると頭を使って考えることがなくなる、とかね。 p77 土井 「料理とはクリエイションである」という考え方と、「料理の最善はなにもしなこと、つまり素材を生かす」という相反する考え方の両方を、私たちはもっています。前者は西洋料理的観念であり、後者は日本料理的観念と言えます。それは西洋の人間中心主義と日本の自然中心主義(観)の結果だと思います。後者は、かつてギリシャのもあったそうですが、自然のなかにすでにあるものから取りだす(take)調理。それは、原初的な食事のスタイルで、日本ではいまだに失わずにあるものと考えています。 p97 中島 民藝という言葉自体は、柳宗悦がつくった言葉で、柳、河井寛次郎、濱田庄司は民藝運動の重要な担い手たちです。彼らが考えたことの根底には、日本の仏教、とくに浄土教の世界があって。今、土井先生がおっしゃられたように、美しいものをつくろうとするから美が逃げていく。それが自力という問題です。それに対して「用の美」。人間が器になったときに、まさにそこに他力としての美がやってくる。この浄土教の世界と、土井先生がおっしゃる「いじりすぎない」とか、「力まかさの料理はやめておこう」という世界観が深く結びついているんだなと思った次第です。 p113 土井 なんでも自分の思いどおりになると考えるのは、たとえばケーキとかパンとかのように、粉や液体のように正確に計量できるものを扱う世界。それでも厳密には同じじゃないんですけどね。それはヨーロッパの科学的思考で、いつも正確に分量をはかって、温度も適正で、ちょっとでも狂ったら違うものになると困るというのは、ロボット的ですね。 →これは違うんじゃ…? わたしはケーキやパンを作るからわかるけど、特にパンは発酵させて作るので、まったくロボット的ではない! 生き物を扱うように、育てるように様子を見ながら作っていく。正確な分量、時間、温度で機械的に作るのではない。「いい加減」を見極める必要がある。 土井先生はなんだか日本を持ち上げて欧米を下げるところがあるなぁ、、と「一汁一菜でよいという提案」を読んだときにも思ったのだけど、p144~148あたりで西洋の良さについて触れているところもあったので(ヨーロッパではスープを自分で好きなように味付けして食べるとか、料理人同士にリスペクトがあるとか)、あれ?別に日本礼讃が過ぎるわけでもなく、公平に見られているのかな?失礼しました…と思ったりもした。
Posted by 
利己主義の時代ではないのだなと思った。利他なんて難しいと思ったけど、家族のことを想って料理を作ることも利他かもと思った。「和える」と「混ぜる」は違うというところは勉強になった。
Posted by 

