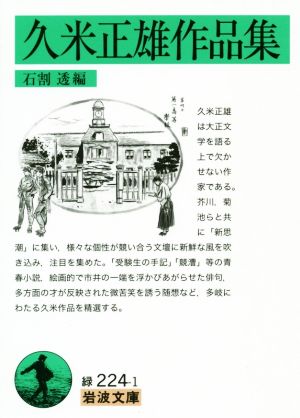
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 文庫
久米正雄作品集 岩波文庫
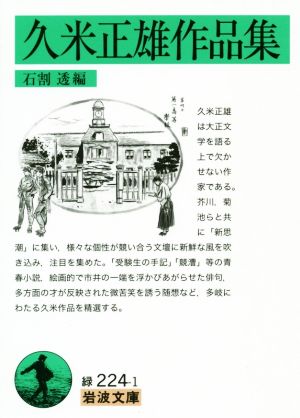
定価 ¥935
¥715 定価より220円(23%)おトク
獲得ポイント6P
在庫あり
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
6/7(金)~6/12(水)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 岩波書店 |
| 発売年月日 | 2019/08/21 |
| JAN | 9784003122419 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
6/7(金)~6/12(水)
- 書籍
- 文庫
久米正雄作品集
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
久米正雄作品集
¥715
在庫あり
商品レビュー
3.8
6件のお客様レビュー
どの作品にも地味なドキドキがあります。「地味な」と言うと語弊があるかもしれませんが、ストーリーが進んでいくけれども何かがおかしい、といった感じでしょうか。
Posted by 
小説は1916(大正5)年から1926(大正15)年に書かれたもの、随筆と俳句は同時期から1949(昭和24)年あたりまでのものが収録されている。 久米正雄という名には、日本近代文学を読んでいるとけっこう頻繁に出会う。文壇内での交友関係も広く、かつ、恐らく大正時代の文壇の中心...
小説は1916(大正5)年から1926(大正15)年に書かれたもの、随筆と俳句は同時期から1949(昭和24)年あたりまでのものが収録されている。 久米正雄という名には、日本近代文学を読んでいるとけっこう頻繁に出会う。文壇内での交友関係も広く、かつ、恐らく大正時代の文壇の中心付近にいた人なのだろう。しかし、こんにち、久米正雄の作品にはなかなか出会えない。紙の書籍としては、現在刊行されているのはこの岩波文庫1冊だけなのではないか。 初めて読んでみた久米正雄の小説は、しかし、なかなかに良かった。ストーリーはシンプル、ストレートで、どこか清々しい。作者自身、素直でオープンな人だったのかもしれない。 文体に魅力がある。読みやすく平易なのだが、ちょっと変わった言葉遣いもあるのが、味わい深い。 本書を読む限り、結構良い小説群である。もっとも小説は本書の2分の1強程度しかなく、もっと読みたくなる。解説を読むと明白に「通俗文学」と呼べるものをも書いたらしいし、意外と多様な作品群を残した作家なのかもしれない。 1891(明治24)年生まれの久米正雄は、菊池寛の3歳下で、1892(明治25)年生まれの芥川龍之介は3月生まれなので、久米と芥川はもしかしたら同じ学年だったかもしれない。 随筆の部の最初にある「芥川龍之介氏の印象」は、高校時代から一緒に過ごしてきた、ごくごく親しい仲間の目で少年-青年期の、マジメで勤勉な芥川像を描き出しており、これはなかなか貴重である。 随筆と言うよりエッセイっぽいこれらの作品は、当時の文壇や世間の様子を刻んでいてなかなか興味深いものがあった。 この作家の本が紙媒体では他に手に入らないというのが、非常に残念だ。
Posted by 
久米正雄氏については、中学時分に郡山市内の中学生を対象とした文学賞に作品を応募していた割に、初めてその作品を読んだ。「私小説と心境小説」(P226~P241)にある 結局、すべての芸術の基礎は、「私」にある。(P233L9) という言葉にも表れているように、彼の小説はその多くが...
久米正雄氏については、中学時分に郡山市内の中学生を対象とした文学賞に作品を応募していた割に、初めてその作品を読んだ。「私小説と心境小説」(P226~P241)にある 結局、すべての芸術の基礎は、「私」にある。(P233L9) という言葉にも表れているように、彼の小説はその多くが極めて私小説的=「……その人々の踏んで来た、一人生の「再現」(P231L16)」であるように感じた。作品としては特に「父の死」「受験生の手記」が心に残っている。両作品に通ずるところとして、変に劇場的な装いがないことがある。これこそは恐らく、久米の「腰の据わり」を表しているためであって、彼が実際にどのような考え方をして生きてきたのか。それを表しているように思った。 「父の死」については、久米が実際にその人生で体験したことがベースとなっているであろうことが予想される。これは俗に「私小説」として考えられている「私小説的」側面であるが、しかし大事なのは、例えば主人公が父の自死した場に直面した際にまず出てきた思いが「母は全身で泣いている!」であった点だと考える。そしてまたその直後に、主人公が父の亡骸を冷静に観察し、その思いを推察している点である。久米は「父が自殺した」という「出来事」を描いたのではなく、「自殺した父を見た自身の感情」を描くことによって、鮮やかに彼の人生観を表したのではないか。そのように考えると、「父の死」という作品は単に日記的なものではない、1人の人間を正に象ったものとなって現前すると考える。 また「流行火事」については少々啓蒙的な装いが色濃く感じられ、「父の死」「競漕」という「私小説」として優秀な作品の後に発表されていることが、少々個人的に疑問を抱いた。童話的な作品を好まない自身の嗜好性が影響しているせいだろうとも思うが、それにしても、少々フィクションとして都合のいい展開が散見されたのではないかと思う。ただ、平吉が恐怖を感じていくその過程には一種魅せられるものがあることも確かであり、その点を考えると、久米は人の心の機微を描くのが真に上手な作家の1人だったのではないかと考える。 短くなってしまったが、随筆については過去の作家たちの生き生きとした生活、及び自分勝手さを感じることができたことが嬉しかったし、また何より、「私小説」同様久米の「腰の据わり」方が随所に見られたことが良かった。これを機に谷崎など好きな作家の随筆も読んでいきたい。
Posted by 


