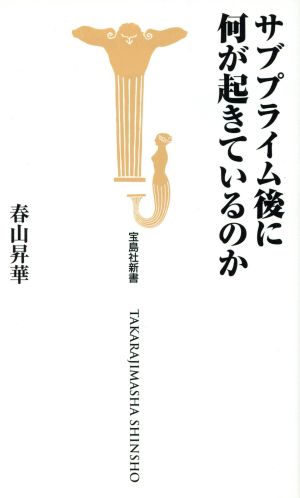
- 中古
- 書籍
- 新書
サブプライム後に何が起きているのか 宝島社新書
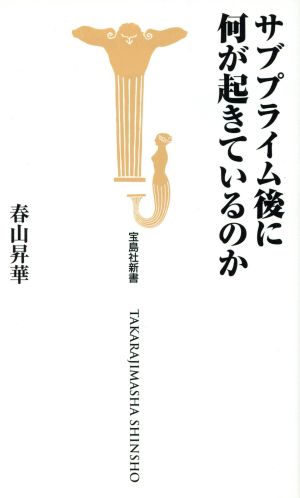
定価 ¥712
¥110 定価より602円(84%)おトク
獲得ポイント1P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 宝島社 |
| 発売年月日 | 2008/04/24 |
| JAN | 9784796663090 |
- 書籍
- 新書
サブプライム後に何が起きているのか
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
サブプライム後に何が起きているのか
¥110
在庫なし
商品レビュー
3.4
21件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2008年刊。サブプライム問題の要因、事後の問題点と現況の解説がなされる。極めて良心的な解説・啓蒙書と思われる。そもそもサブプライム問題は、バブル現象としては特殊ではない。かつて日本が経験したそれのみならず、ブラックマンデー等とほとんど変わらない。むしろ、特殊性は、レバレッジを可能にした証券化技術のため被害が一気に巨大化したという点にあるのだ。本書はこの証券化技術・レバレッジ投資の問題を正しく指摘。「レバレッジは、面白いように利益を増やす…しかし、物事が…反対に動いた時の破壊力もすさまじい」と。 その上で、日本のレバレッジ取引の典型たるFX(外国為替証拠金(保証金)取引)の問題も同様と喝破するのだ。さて、本書によれば、現況のアメリカを支援しているのが国富ファンド(中近東イスラムの石油マネーと中国マネー。誕生は米国貿易赤字継続の産物)である。緊急避難時はともかく、米国がこれらに依存し続けるとは、政治的には想定しにくい。この点は、著者は過小評価していないだろうか? 検討課題。①ドル・キャリートレード、②イスラム金融。利息禁止・利用料や割賦販売手数料を実質利息と見る方法論。③企業融資から消費者へのシフト。情報の非対称性のため有利な取引が可能。④格付け機関(唯一の情報源。AAA)とモノライン保証会社(保証契約締結)による拡販。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
サブプライム問題中盤戦について、書かれた一冊。 前半とか中盤、後半といった概念は私個人の感想で しかないです。でも、リーマンショックが入っていないと 後半戦とは呼べない気がしてしまって・・・。 それでも、リーマンショックの半年前に、ここまで サブプライム後のことが明確に予測できているのが すごすぎる。 そして、サブプライム問題の本質と思われる 証券化とレバレッジバブルの仕組みが詳細かつ 簡易に記されています。
Posted by 
今年(2008年)9月にサブプライムショックによる大幅な株式市場の下落が始まって、あっという間に、史上最高といわれていた上半期の売り上げが急変しました。 サブプライム問題は今後10年以上長引きそうな予感がします、この問題は奥が深くまだ何がおきているのか私はまったく分かりません...
今年(2008年)9月にサブプライムショックによる大幅な株式市場の下落が始まって、あっという間に、史上最高といわれていた上半期の売り上げが急変しました。 サブプライム問題は今後10年以上長引きそうな予感がします、この問題は奥が深くまだ何がおきているのか私はまったく分かりません。ただおぼろげながら予想できるのは、この変化は、911テロに続く、一種の金融テロに近い形で、私たちの根本を変えていくと思われます。 激動の時代を体験できる良いチャンスと捕らえて、サブプライムに関する情報収集を今後も続けて生きたいと思いました。 以下は気になったポイントです。 ・現在起きているドル・キャリートレードは、ドルを売って高金利国ブラジルのレアルを買うこと、これはバフェットも実施中である、ドル金利がゼロになれば、殆どどの通貨に対してもこの取引が成立する(p51) ・邦銀のサブプライム損失が比較的少ないのは、公的資金注入により、監視状態が続いたから、対象外であった証券業界(野村證券、みずほFG)は絡んでいる(p55) ・シティグループの07,4Qの決算は、創業初の大赤字(1.6兆円)、サブプライム関連の損失は2兆円、1.6兆円の優先株発行(p68) ・欧米の金融機関がアジア・中東の国富ファンドに頼っているのは、面子を捨てた最後の手段(p78) ・様々な国の貿易黒字の累計(外貨準備高)は、アメリカの貿易赤字金額の累計と言い換えられる(p87) ・中東諸国にとって、手持ちの外貨準備の価値(購買力)を維持するには、1) 中東通貨をユーロに対して下がらないようにする(=ドルペッグ廃止)か、2)ドルペッグを維持しつつ外貨準備を増加(=原油価格の上昇)である(p90) ・シティとメリルの出資で、クウェート通貨庁・アブダビ投資庁・韓国投資公社が勝ち取った条件は、配当率11%(p98) ・証券化された商品を購入させる「お墨付き」として登場したのが、格付け機関・モノライン保険会社、である(p125) ・企業に関する格付けではトリプルAは、ほんのわずかしか存在しないが、証券化商品では、ほとんどがトリプルAである(p161) ・大英帝国は、大幅なインド・中国への貿易赤字を取り返すために、アヘンを中国へ輸出した、これがアヘン戦争の原因となる(p184)
Posted by 



